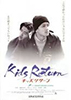MAGAZINE
Do it MagazineDo it Theaterが注目のシアターカルチャーをクローズアップする企画[Do it Close-up]。今回は、古都・京都を舞台に、京都愛の強すぎる女性が引き起こす大騒動を描いたシニカルコメディ 映画『ぶぶ漬けどうどす』の冨永昌敬監督にインタビュー。「住む人の目線」で街を捉え、町家での撮影にも独自の視点を貫いた本作。京都という街から見えてくる、習慣と文化のあり方、そして映画づくりにおける「選択」についてお話を伺いました。
6 月 6 日(金)テアトル新宿ほか公開
京都の老舗扇子店の長男と結婚し、東京からやってきたフリーライターのまどかは、数百年の歴史を誇る老舗の暮らしぶりをコミックエッセイにしようと、義実家や街の女将さんたちの取材を始める。ところが、「本音と建前」の文化を甘く見ていたせいで、気づけば女将さんたちの怒りを買ってしまう。猛省したまどかは、京都の正しき伝道師になるべく努力するが、事態は街中を巻き込んで思わぬ方向に──。
01“決まりごと”をもう一度選び直す映画づくり
――今回は「街と文化と人」というテーマでお話を伺っていきたいと思います。作品、とても面白く拝見しました。映画全体を通して、京都の街並みがとても美しく映し出されているなと感じました。
街並みを見せるシーンは、冒頭のタイトルバックに集約しています。京都に到着した深川麻衣さんと大友律くんが、京都駅から路線バスで松原通りの家へ向かう道中、そして将軍塚の山の上から望遠レンズで撮影した風景、家の台所の様子などをモンタージュしています。タイトル以降は、「京都という街」よりも「京都の家」を見せることに重きを置きました。
 冨永昌敬(監督)|1975年生まれ、愛媛県出身。 おもな映画作品は『亀虫』(03)、『パビリオン山椒魚』(06)、『コンナオトナノオンナノコ』(07)、『シャーリーの転落人生』(08)、『パンドラの匣』(09)、『乱暴と待機』(10)、『目を閉じてギラギラ』(11)、『ローリング』(15)、『南瓜とマヨネーズ』(17)、『素敵なダイナマイトスキャンダル』(18)。ドラマ作品には「ひとりキャンプで食って寝る」(19/TX)、「彼女のウラ世界」(21/FOD)、「僕の手を売ります」(23/FOD)などがある。 前作『白鍵と黒鍵の間に』(23)は、フランスのKinotayo映画祭コンペティションにて審査員賞を受賞した他、Japan Cuts(ニューヨーク)、台北金馬映画祭や香港国際映画祭などに正式出品され、海外でも高い注目を集めた。
冨永昌敬(監督)|1975年生まれ、愛媛県出身。 おもな映画作品は『亀虫』(03)、『パビリオン山椒魚』(06)、『コンナオトナノオンナノコ』(07)、『シャーリーの転落人生』(08)、『パンドラの匣』(09)、『乱暴と待機』(10)、『目を閉じてギラギラ』(11)、『ローリング』(15)、『南瓜とマヨネーズ』(17)、『素敵なダイナマイトスキャンダル』(18)。ドラマ作品には「ひとりキャンプで食って寝る」(19/TX)、「彼女のウラ世界」(21/FOD)、「僕の手を売ります」(23/FOD)などがある。 前作『白鍵と黒鍵の間に』(23)は、フランスのKinotayo映画祭コンペティションにて審査員賞を受賞した他、Japan Cuts(ニューヨーク)、台北金馬映画祭や香港国際映画祭などに正式出品され、海外でも高い注目を集めた。
――どのようなこだわりがあったのでしょうか?
あれは“こだわり”というより、ご挨拶のつもりですね。映画が始まってから街があまり出てこなくても、そこが京都だと忘れないでいてくれるように、という意図でした。それでタイトルのシークエンスが長くなったのは、エンドロールを付けない方針だったことも影響しています。
――なるほど、最初に京都を提示するための構成だったんですね。なぜエンドロールをなくそうと思ったのでしょうか?
ラストシーンのあとにエンドロールがあると、どうしても余韻みたいな時間が生まれます。それを避けたかったのも理由の一つですね。「終」のマークが出てすぐに劇場が明るくなるような時間の使い方が、この作品にはふさわしいと思っていました。

――とても面白い試みですね。
ロケ場所などの協力クレジットだけは、最初に出すと展開がバレてしまうので最後にしましたが、それも扇子の形に見えるようにレイアウトしています。そういう趣向を凝らしたくなったのは、京都という舞台にもヒントがありました。京都では何でも街や家に馴染むようにデザインが工夫されてますよね。クレジットタイトルを出すのにも、どうにか作品の狙いに馴染ませたいですから、この作品では特に意識しました。
――エンドロールの有無も含めて、形式そのものを意識した構成だったんですね。
そうですね。アサダさんとも脚本段階からそういう話をしていて、参考にしていたのは50〜60年代の日本映画でした。その時代はエンドロールがない作品が多いんです。
――なるほど。あの冒頭の風景のシーンは、映画の歴史をもう一回見つめ直す、挑戦的な意味も込められていたんですね。
はい、大袈裟に言えばそうです(笑)。

02京都を特徴づける風景とは──記憶に焼きついたアングル
街の話でいうと、僕は京都の「屋根」が印象的だと思っていて。道よりも、屋根のラインが美しいなと。
――確かに、作中で映し出される瓦屋根のシーンも印象に残っています。
京都の建物は木造の2階建てが多くて、瓦屋根がずらっと並んでいます。あのシーンは、昔観た映画を参考にしているんです。
――どんな映画だったんですか?
市川崑監督の『東京オリンピック』というドキュメンタリー映画です。1964年の東京五輪を撮ったもので、冒頭に聖火ランナーがルートをずっと走ってるシーンがあるんですけど、各地の著名な場所が映し出される中、京都を通るとき、画面の半分以上が瓦屋根っていうアングルだったんですよ。それがすごく印象に残ってて。
――そのシーンが記憶に残っていたんですね。
そうですね。学生のときに観てから30年くらい、ずっと頭に残っていました。今回ああいうカットを撮りたいなと思って、カメラポジションを探しましたが、技術的にはドローンがあるけど、京都は飛ばせないエリアが多くて。真上からの撮影はなかなか難しかったです。

03「理由がわからないけど続ける」──習慣から文化が続くということ
――映画の中で、建物の内部も印象的でした。たとえば、まどかが女将さんたちに「お礼」を言われに料亭に入っていき、長い廊下を歩いていくあのシーンは、日本的だけど、少し異世界感も感じました。
実際の造りはもっと単純で、あの廊下は2回曲がれば奥の座敷に行けるんです。ただ、そのままでは「お礼」の複雑な意味合いが感じられません。まどかに、どこへ連れて行かれるんだろうと思わせたいので、歩いていく彼女たちを見送るようなアングルと、逆に迎えるようなアングルを編集で組み合わせて、廊下を5回ほど曲がっているように誇張しました。
――なるほど。廊下のシーンは特に京都特有の面白さを感じるシーンでした。
京都の家は間口が狭くて奥に長いといわれる通りです。メインの舞台で撮影にお借りした大西常商店さんは、家の奥行きの長さが生活の動線そのもので、本当に理想的なお家でした。
 ©2025「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会
©2025「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会
――でも、だからこそすごくリアリティがありました。京都の生活空間がしっかり映っている感じがして。同じ日本だけど、違う文化圏の生活を覗き見ているような感覚になりました。
そう言っていただけるのは嬉しいですね。観光目線ではなくて、そこに住んでいる人たちの視点で描きたかったんです。なので、実際に京都で商売をしている方々に取材もしました。
――どんなことを伺ったんですか?
たとえば、季節ごとの行事とか、昔からの習慣についてです。でも皆さん、「なぜそれをしているのか」は分からないと言うんですよ。「昔からやってるから」って(笑)。でも絶対にやめない。理由が分からなくても続けているんです。
――その「理由がわからないけど続ける」というのが、文化や伝統が続いていることのような気がします(笑)。
そう思います。合理的じゃなくても、無駄に見えても、やめない。それが長く続いてきたことの重みというか。毎月1日と15日にお赤飯を食べる習慣って、どうせ食べないでしょって思うんですけど、ちゃんとその日になると赤飯が届いて、食べたくないかもしれないけど食べる。その理由がわからないってことは、歴史の厚みですからね。
――形式や理屈じゃなくて、体に染みついたものとして続いているというか。
まさにそう。合理的に考えたら「やらなくてもいいんじゃない?」っていうこともあるんですけど、それでも続けている。
まどかと環が最後に衝突するのも、そういう“中の人”と“外の人”の視点のズレを描きたかったんです。

――たとえばお祭りとかも、「なぜやってるか」はあんまり気にしないけど、みんな当たり前に続けてますよね。
お祭りに関しては、起源はあるにはあるんだけど、だいたい伝説とか、五穀豊穣を願ってとか、商売繁盛のためとか、そういう“もっともらしい話”が多いですよね(笑)。でも今の人たちは、そういう由来を深く考えてないんじゃないかなって思います。日々の暮らしの中で無理なくお祭りが組み込まれてるっていうか。
――なるほど。京都って特に、大小のお祭りがものすごく多いですもんね。
そうですね。人によっては毎週何かしらの行事があるくらい。商店街単位の小さいものから、祇園祭みたいな大きいものまで。それがずっと続いてるっていうのは、やっぱりすごい文化ですよ。
 ©2025「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会
©2025「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会
――まどかが街中の鳥居によくわからないけどとりあえず拝むシーンがありましたけど、あれもすごく面白かったです。
あのシーンというか、あの鳥居が面白いですよね。僕も最初は知らなかったんですよ。脚本のアサダさんが書いてて「こんな鳥居あるの?」って聞いたら、「あると思います」って言われて(笑)。実際、現地で探してみたら、ほんとにあったんですよ。でも、それまで何度も通ってたのに全然気づいてなくて。たぶん、実際に小便しようとしないと見えない場所にあったんですよね(笑)。
04映画館で初めて映画監督に出会った日―冨永監督の記憶に残るシアター体験
――最後に、毎回インタビューでお伺いしているんですが、監督にとって記憶に残っている映画体験ってありますか?
それで言うと、大学1年のときにテアトル新宿で今村昌平特集をやってたんですよ。それを観に行ったときの体験が思い浮かんだんですが、今村監督ご本人がその上映会場に来ていて。
――それはすごいですね!
そうなんです。それまで“映画監督”っていう人を実際に見たことがなかったので、衝撃でした。しかもそのとき、上映中にフィルムが切れたかなんかで、一回止まっちゃって。お客さんがざわざわしてたら、今村さんが自分から舞台に出てきて、「これは劇場のせいじゃないんです!」って言ったんですよ。「映画会社のフィルム管理がまずかったんです」と。
――かっこいい……!
あの姿は今でもすごく覚えてますね。映画館で映画のことについて、観客に向かって語るっていう行動を初めて見て。ああ、映画監督ってこういう人なんだなって思いました。あれはほんと、極端な例だったかもしれないけど、自分の中ではすごく記憶に残ってます。

05作品情報
映画『ぶぶ漬けどうどす』
6 月 6 日(金)テアトル新宿ほか公開

出演:
深川麻衣
小野寺ずる 片岡礼子 大友律 / 若葉竜也
山下知子 森レイ子 幸野紘子 守屋えみ 尾本貴史 遠藤隆太
松尾貴史 豊原功補
室井滋
監督:冨永昌敬
企画・脚本:アサダアツシ
音楽:高良久美子/芳垣安洋
製作:清水伸司/太田和宏/勝股英夫/小林栄太朗/佐藤央 企画・プロデュース:福嶋更一郎 エグゼクティブ・プロデューサ ー:松岡雄浩/西澤彰弘 プロデューサー:石川真吾/横山蘭平 アソシエイト・プロデューサー:三好保洋 ライン・プロデューサ ー:柄本かのこ 協力プロデューサー:荒木孝眞
撮影:蔦井孝洋 照明:石田健司 録音:山本タカアキ 美術:福島奈央花 装飾:遠藤善人 助監督:中薗大雅 制作担当:福島伸司 スタイリスト:小磯和代 ヘアメイクデザイン:西村佳苗子 編集:堀切基和 宣伝プロデューサー:山根匡子
製作幹事:メ~テレ/東京テアトル 制作・配給:東京テアトル 制作プロダクション:さざなみ
「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会:メ~テレ/東京テアトル/エイベックス・ピクチャーズ/テンカラット/ワンダーストラック
©2025「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会
公式サイト:bubuduke.jp 公式 X:@bubuduke_movie
photo:加藤千雅(@kazumasakato_)
interview&text:reika hidaka