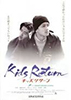MAGAZINE
Do it Magazine01春とヒコーキ 土岡哲朗さんのシゴトとシネマ
映画との出会いはいつも偶然で、何気なく観た映画が、人生の一本になったりする。【シゴトとシネマ】では、仕事や生き方に影響を与えた、働くことの原動力になっている映画とエピソードを教えていただきます。今回は、お笑い芸人 春とヒコーキ 土岡哲朗さんの人生を揺るがせた映画と、仕事への想いをご紹介。
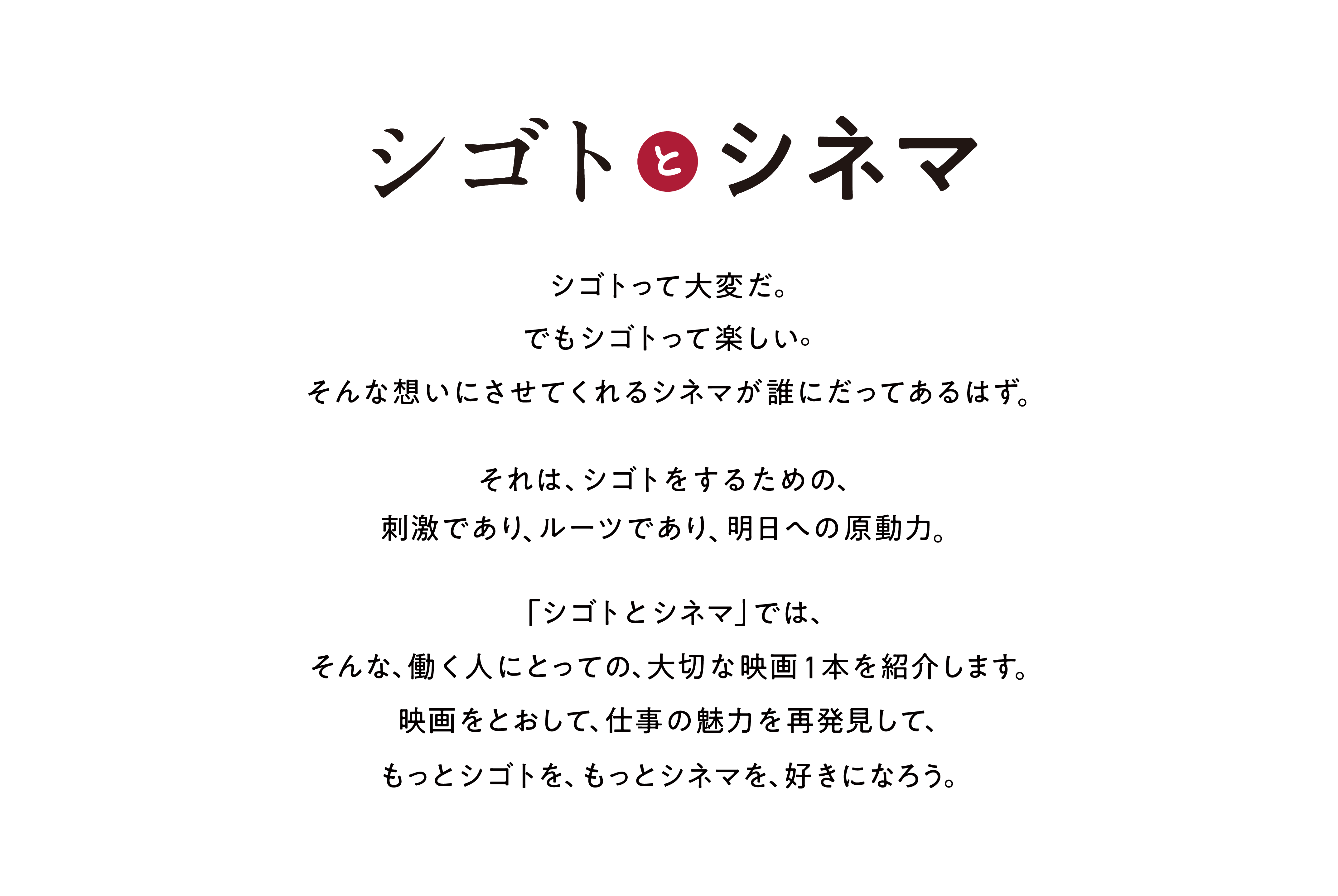
02作品名
映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』
監督:ジョン・ワッツ

デジタル配信中
発売・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & ™ 2024 MARVEL.
03インタビュー
――なぜこの作品を選ばれたのでしょうか?
芸人になって何年か経ったころ、憧れていた仕事をしているはずなのに、いろいろと考えることが生まれてきてしまうことがあって。そんな時期に『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』を観て、すごく刺さるものがありました。仕事を始めるきっかけみたいな映画ではないんですけど、もう1度芸人として踏ん張る気持ちを思い出させてくれた作品ですね。主人公に共感しながら、自分と重ねて観た映画なのですごく記憶に残っています。

――1人の若者としても、ヒーローとしても、 また1歩成長するみたいなストーリーでしたよね。
そうですね。『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』は、スパイダーマンがヒーローとして認められて、憧れのアベンジャーズの一員になったけど、ヒーローとしての活動よりも自分のこと(夏休みの旅行)を優先するんですよね。その、ヒーローとプライベートのことで板挟みになっている感じが、そのときの自分とどこか重なったんです。
――なるほど。
芸歴を重ねて少し疲れてしまったときの「自分が楽しむ時間も欲しい!」という気持ちにリンクして、グッときた作品です。あと、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のようにヒーローの仕事から逃げようとするヒーローって見たことなかったし、その感覚がめちゃくちゃリアルで、自分に近い感じもあって、ヒーロー映画で初めて共感しました。

――当時の状況が似ていて、刺激を受けた作品だったんですね。
そういう意味で言うと、影響を受けた作品は実はもう1作品ありまして……。
――なんと! どの作品でしょうか?
2015年に観た『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』です。既に前の人たちが伝説を作っているけれど、自分たちも前の世代の人たちのように何かをやりたい!というようなお話で、これまたすごく刺さる内容だったんです。そして、制作者側の若いクリエイターたちからも、伝説になっている作品のバトンを引き継いで「レジェンドたちを超えるような作品を作りたい」という想いが伝わってきたんですよね。
――内容もだし、制作側の想いにも引き込まれるものがあったと。
芸人として、既に先輩たちがいろいろなことをやり尽くしてしまっているので、超えられることが何もないな……と思ってしまっていたんです。でも、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』を見たときに、自分たちもジェダイになりたいし、言い訳せずにやりたいんだったらやらなきゃ損だなと思えて。ずっと好きだった映画の新作が自分の背中を押してくれて、そこから芸人として歩んでいく勇気が出たことを覚えています。

――今回Do it magazineで取材するきっかけにもなった、Filmarks(フィルマークス)でのレビューですが、なぜ書き始めたのでしょうか?
大学生のころに、映画を趣味にしようと思い立って、観た映画をExcelで記録していったのが始まりです。最初は一言メモくらいから始めたんですけど、メモを見返したときに、どんな話だったかあまり思い出せないことがあって(笑)。ストーリーもですけど、観たときの自分の気持ちを思い出せるように、だんだんと詳しく書くようにしました。
――いろんな作品を観ていくと、細かい部分は忘れてしまいますよね。
ちゃんと感想をまとめるようになってから、「今観た映画って、こういう映画だったんだ」って、自分の中で整理できるようになっていったんです。「俺が今見た映画ってこんな作品だったんだ」って客観的に気付くことができたり、「人間のこういう面を描いていた作品だったんだ」みたいなことがわかるようになってきたりして。
――書き始めたことで、映画への理解も深まっていったんですね。
はい。でも、これまで13年間、誰に見せるわけでもなく、自分のパソコンの中で習慣として書き続けていただけだったんです(笑)。なので、少し前にマネージャーさんが「映画好きだったらFilmarksをやった方がいいよ」と教えてくれて。芸人としてもっと自己アピールをしていかないとと思っていたので、Filmarksで感想を書き始めたんです。感想を書くようになってからリアクションをもらえる機会が増えてきたので、書いたものを誰かに見せるのってめちゃくちゃ大事だなと思いました。

――映画の感想はどんな視点でまとめて書いていくことが多いんですか?
いくつかあるんですけど、1つは好きなシーンを3つくらい思い出して、なぜそのシーンが好きだったのか、どんな意味のあるシーンだったのか、ということを書いています。これは僕の映画のYouTubeチャンネル『映画の話をドガチャガ』を始めてから気付いたんですけど、映画の感想を話すときに好きなシーンを3つずつまとめて書いておくと喋りやすくなるんです。
――自分の視点でポイントをまとめていくような感じですね。
もう1つは、「主人公がどう変わったのか」というところ。その“変化”が成長のときもあれば、酷い目にあって元の人とは違う人のようになってしまうときもあるんですけど、ほとんどの面白い映画は、良くも悪くも主人公がちょっと変わってしまうんです。主人公が、どこで非日常になって、どこで変わって、なぜ戻ってこれなくなってしまったのか、みたいなところに注目してまとめるようにしています。ニートのときに読んだ「映画は父を殺すためにある」という本に書かれていたんですよね。

――面白いですね。そういった映画を観るときの視点は、芸人としてネタを作るときにも活かされたりするのでしょうか?
ネタを書くことに関してだと、「脚本の“三幕構成”」みたいな本が参考になりました。どんな物語も始まりがあって終わりがあって、その“間”がある。なので、2時間の映画だったら、始まり=30分、間=60分、終わり=30分という配分になるので、映画が始まって30分経ったところで何が起きたかが大切なんだなと。
――なるほど。
正直、お笑いは面白いボケがあれば、ストーリーはなくてもいいんじゃないかって思っていたんです。でも、その本を読んでから、本当にいいネタは笑いながらも、話としてちゃんとオチがついていることが必要だと思うようになりました。途中でぶん投げて終わってしまうと、どんなに面白くても、ふわっとして終わってしまう。なので、ちゃんとお笑いを成立させるためにも、余計な見づらさは省かなければいけない。最初に起きたトラブルに対して、最後には何かしらの結論を出さなきゃいけないんだよなと。
――芸人さんって映画好きな方が多いイメージがありますが、楽屋とかで映画の話をすることもありますか?
話しますね。知り合ったばかりの人とでも映画の話で仲良くなることもありますし。楽屋で映画の話をしている人は仲良くなれるタイプの芸人なんだなっていう1つの基準になることもあります(笑)。
――映画の観方って人それぞれなので、話を聞くのも面白いですよね。そういう捉え方もあったんだ、みたいな。
そうですね。映画の話から自然と生い立ちやこれまでの環境の話に発展して、その人の人となりが見えてくることもあるんです。あと、マニアックな映画とか、自分の知らない映画の話を聞くと、「なんでその映画に辿り着いたのか」とか「何が好きでどんな趣味なのか」みたいな話に発展することもあります。

――土岡さんが映画を観たくなるときって、どんな気分のときが多いですか?
新作でいうと、ニュースやSNSで映画の情報を得たときですね。毎年、何かしらのシリーズものの映画がお祭りみたいに盛り上がるので、そのお祭りには乗っかっておきたいなという気持ちがあります(笑)。あとは大きな1つの仕事が終わったときなど、“どこかに出かける”、“冒険に行く”みたいな感覚で観ることが多いです。
――映画はいろんな世界に連れて行ってくれますもんね。
映画を観ると脳の中がどんどん広がっていく感じがあるんです。なので、自分のフィールドを広げたいときに観ることもあります。あとは、何かに飽きてしまったときとか、見えている世界に慣れてしまったときとか。「まだまだこんな世界があるんだ!」ということを知りたくて、映画を観ることが多いかもしれません。

――今ではジャンルを問わず幅広くいろんな作品を観ている土岡さんですが、観る映画はどのように開拓していったんですか?
高校生までは、ハリウッドの大作映画とかアクション映画くらいしか観ていなかったんです。大学生のころにいわゆる“名作”を観るようになってから、ジャンルが広がったような気がしています。“名作”の中には自分の守備範囲ではなかった作品との出会いもあったので、全然わからなかった映画もたくさんあるんです。例えば、当時は全然わからなかった『ゴッドファーザー』も、25歳のころ観返したらめちゃくちゃ面白いなと思って。まずは「観た」という経験を重ねて、映画好きレベルを上げていました(笑)。
――書き続けてきた映画の感想メモがめちゃくちゃ活きそうですね。
『スターウォーズ』シリーズも観るたびに全然違って見えてくるんですよね。好きな映画でさえ観る度に感想が変わるし、観るときのコンディションにもよると思うので、1度観てあまりよくわからなかった映画もまたいつか観てみようと思っています。結局人生は、「自分の頭の中をどうしていくか次第」なんだろうなって思うんです。
――どういうことでしょう?
ものの見方を自分の中でどう築いていくのか、柔軟にいろんな形で世界を見られるようにして、広く深く、自分を拡張していくという感じですね。映画を観ていると、自分の内側をもっと広げていきたいっていう気持ちになってくるので。

――映画は子供のころからよく観ていたんですか?
親が映画好きだったので、子供のころから『ドラえもん』とか『トイ・ストーリー』とかいろいろ観ていました。その中でも、映画好きだなって思ったきっかけの作品は『スター・ウォーズ』だったと思います。もともとは父親が『スター・ウォーズ』を好きで、新作の度に父親と一緒に映画館で観ていたんです。でも、『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』を観に行くときに、もっと『スター・ウォーズ』のことをちゃんと知ってから観たい!と思って、父親が買ってきてくれたこれまでのエピソードのDVDを観てから行きました。そこから前のめりで映画を観るようになりましたね。
――お父様の影響が大きかったんですね。
あと、金曜ロードショーで一緒に『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』を観ていたときに、父親がいろいろ説明してくれていて。先の展開を知っていて、自分にはわからないことを教えてくれていた父親の姿がちょっとかっこよく見えてしまったんですよね(笑)。『猿の惑星』とかも意味がわからなかったけど、父親の説明を聞いて、ちょっとゾッとしたこととか覚えています。
――欠かさずに観ている監督、俳優の映画ってありますか?
タランティーノ監督と、全作は観れていないですけどスピルバーグ監督の作品ですね。スピルバーグ監督の作品は『E.T.』『ジュラシック・パーク』『未知との遭遇』あたりがすごく印象に残っています。『ジュラシック・パーク』は、恐竜が本格的でめちゃくちゃ怖かったんですけど、それがすごく嬉しくて。想像力って、楽しいことを思い浮かべる力もあるけど、怖いことを思い浮かべるものでもある。だから、映像が怖ければ怖いほど、「想像力ってこんな幅広いんだ」って感じることができたんです。
――なるほど。
あと、『E.T.』も宇宙人が出てくる話ですけど、小学生のころって「この神社の奥に行ったら映画のような世界が広がっているかもしれない……」とかいろいろ妄想して、友達と遊んだりしていたはずで。だから、映画の中で男の子が宇宙人と過ごしていることって、フィクションだけど現実だなとも思えたんです。映画は、“夢だけど現実だよ”って提示できるものだし、そこがかっこいいなと感じています。

――土岡さんが仕事で大事にしていることを教えてください。
あまり“仕事”という言葉に収めないようにすることですかね。スケジュールを確認する時も、「明日は仕事だ」ではなく「明日はライブだ」と捉えるようにしています。「明日は仕事だ」と発するだけで、僕の中では違う形になってしまう。芸人の活動は、“仕事”ではなく、“お笑い”という呼び方にしておきたいんですよね。多分それは僕がニートだったからというのもあると思うんですけど。
――捉え方を変えることで、向き合い方も変わりそうです。
僕の中で、“仕事”に対してどこかネガティブでドライなイメージがあるんです。そう感じると頑張れないし、やり甲斐や楽しさとかを感じられなくなってしまう。なのであまり“仕事”とは捉えずに、いつも「お笑いをやるぞ!」みたいな気持ちで取り組んでいます。良くも悪くも、楽しい面も辛い面も、「冒険する」みたいな気持ちで取り組んでいたいので。
――では最後に。土岡さんにとって、映画ってどんな存在ですか?
人生経験ができる場所だと思うので、「疑似体験」ですかね? 映画を1本観たら、何か月も何年も、人生を送らないと行きつかないような気持ちに、2~3時間でなれるから。「人生の拡張ソフト」のようなものかもしれません。


04プロフィール
 土岡哲朗
土岡哲朗
お笑いコンビ「春とヒコーキ」のネタ作り担当。2017年4月結成。タイタン所属。
青山学院大学文学部日本文学科卒業。大学卒業後は就職せず、3年間ニートを経験。
X :@tsuchioka_t
Filmarks :@tsuchioka
YouTube バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】:https://www.youtube.com/@bakibakiDT
YouTube 春とヒコーキ:https://www.youtube.com/@haru-to-hikoki
photo:Natsuko Saito(@72527n)
interview&text:Sayaka Yabe