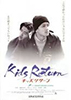MAGAZINE
Do it MagazineDo it Theaterが今気になるシアターカルチャーをクローズアップしてお届けする[Do it Close-up]。 今回は、映画『満月、世界』(2024年9月21日公開)の塚⽥万理奈監督にインタビュー。16mmフィルムで10年かけて子供たちを撮影するプロジェクト『刻』から生まれたオムニバス作品『満月』『世界』。作品を撮るきっかけとなった子供達との出会いや、”音”へのこだわりを伺いました。
『満月、世界』
9月21日(土)より渋谷ユーロスペースほか全国順次公開
01インタビュー
――『満月、世界』は『刻』から生まれたオムニバス作品と伺いました。どのようなきっかけで作品が生まれたのでしょうか?
『刻』は私が中学時代の友人と再会したことがきっかけで生まれた作品です。友人と再会したときに、当時の気持ちや、大人になるまでの自分の気持ちを残しておきたいなと思ったんです。そこから、自分の経験を元にして中学時代から大人になるまでの10年くらいのストーリーを劇映画として書きました。

――そのときには実際に10年かけて撮影する構想があったのでしょうか?
そうですね。映画というものはフィクションで、映画を作る人は、いかに本物になれるかどうかと戦ってきていると思うんですけど、私もずっと格闘してきました。
ある人の物語を描くときに、大人役・子役って分けることがあると思うんですけど、私はそれがあまり好きじゃなくて。私の人生って私しか歩んでいないから、一人の人生は一人が演じるべきだと思ったんです。

――『刻』を撮影されている中で、たくさんの子供達と出会われたと思います。その中でも満月ちゃんとあきちゃんにフォーカスしよう思ったのはなぜですか?
二人とは『刻』に出演してくれる子供達と出会うために行った映像のワークショップで出会いました。子供達はみんなそれぞれ悩みがあって、一生懸命生きていて、未来がいっぱいあって美しいんですけど、満月はその象徴的な子だなと思ったというか。
満月は自分のことを客観的に分かっているけど、モヤモヤしているところもありました。それがすごく可能性を持っていると感じたんです。
――運命的な出会いだったんですね。
そうですね。あきちゃんは『刻』の撮影期間中に「自分の作文を読んでほしい。」と連絡がきたのがきっかけでした。なんだろうと思って読んでみたら、自身の吃音のことを書いた作文で。私は一緒に映画を撮っているのに、あきちゃんが吃音だってことに全く気づいていませんでした。確かに、あきちゃんは何か重たい物を抱えて毎回撮影に来ている感じはしていたんですけど、なんだろうと思っていたんです。
――そうだったんですね。
その作文には、あきちゃんが自分のことを知って欲しくて、どれほど悔しかったのかというのが書いてあって。それを読んだときに、あきちゃんの声を残しておかないとダメだなと思ったんです。
満月のときは子供達と出会ったばっかりで、私が子供達をどう思ったのかという視点はありませんでした。ただただ満月を撮ったという感じだったんですが、あきちゃんに対しては私が言い返せることがあると思ったんです。「私はずっとあなたを見てきたけど、あなた綺麗だったよ。」と言える時間があった気がしたので、あきちゃんという光がどれほど周りの人を励ましているかという視点を入れて撮りました。

――『満月』では満月が踊るシーンがとても美しく印象的でした。あのシーンはどのようにして生まれたのでしょう?
満月は普段から自分で好きに踊ったりするのを学校帰りに撮影している子でした。それをワークショップで制作したセルフドキュメンタリーに入れてくれてて、それがすごく綺麗だったんです。もう泣けるくらい綺麗で。
満月が好きなものを体現している説得力があるなと思ったので、絶対に撮ろうと思いました。満月の踊っている姿を見れば「この子達を残さないといけない。」ってみんな思ってくれるんじゃないかと思って。
あの子たちの好きなものや、何かを好きと思う気持ち、好きでいられる余裕とかを絶対に残さないといけないってみんなに思ってもらいたいなと。

――そのシーンでは今までの満月の会話・セリフが流れますが、どういう意図でしょうか?
満月はいつもイヤフォンで音楽を聴いているんですけど、満月が聴いている音楽は満月だけのものだと思っていて。観客のために聴かせるべきじゃないと思ったというか。
じゃあ満月が踊っているときに無音にするのか、動作音だけにするのかと色々考えたんですけど、満月はこの世界の中で踊っているって思って。満月の世界の中で、あの子はとにかくもがいて踊っていると思ったので、満月の世界の音を全部使おうと思い、結果撮影のときに録音した全ての音を使いました。
――なるほど。反対に、『世界』は静寂で無音な瞬間も長いなと感じました。
そうですね。『世界』に関しては、あきちゃんが言葉に格闘してきたので、中々言葉が出ないという静寂さがありました。あとは、私は元々映画の音楽が少し苦手で…。例えば、生活している中で、感動したときに感動的な音楽って流れないじゃないですか。あれはやっぱり演出だなというか、映画の音楽はお客さんに感情を届ける素晴らしい役目をしていると思うんですけど、私はあまり得意じゃなくて。それを『世界』では素直に表しました。

――静寂なことに不安は感じませんでしたか?
あまり不安は感じませんでした。私はすごく不親切な監督なんです。何かを伝えるためにキャラクターや映画に説明をさせちゃうと、本物から遠くなると思っていて。不安に思っているときって、その人が「不安なの。」って言ってくれないじゃないですか。言葉ではなく表情やその場の空気で「今不安なんだろうな。」と感じ取るから、こっちが読みにいきたいみたいなという気持ちがあります。
――確かにそうですよね。
分かるように演出するのが監督なので、多少のヒントは残しています。ただ、分かりやすくはしていないですね。分からなくても、それ自体がその人の感情だし、100%全ての人に届くことって絶対にないので、その人が好きなように受け取ってくれたらいいかなって思っています。

――海外の映画祭での上映はいかがでしたか?伝わっている実感はありましたでしょうか?
はい、ありました。海外だからこそ、言葉じゃない部分で伝わっているなと感じることが多くて嬉しかったです。
――どういう部分が伝わっていると感じましたか?
「あの子たちは綺麗だ。」ということが伝わっているなと感じました。満月とかあきちゃんに共感したとかではなく、あの子たちの表情で、あの子たちが不安に思っているとか、楽しいと思っているとか、あの子たちが美しいということが伝わっているなと。
――そういった子供達の表情を伝えるために、大切にしていたことはありますか?
満月やあきちゃんにあの美しさを出してもらうためには、あの子たちの不安とか必死さとか、そういうものをそのまま撮影現場に持ってきてもらわないといけませんでした。というより、持ってきてもらえる現場と私たちでいないといけなかった。子供達に「私たちは否定しない」という絶大な信頼をもらわないと撮れない表情だと思っていたので、そういうところを一番に考えましたね。
――それは直接言葉で伝えるのでしょうか?
「あなたのこと否定しないよ」と言っても信じてもらえないので、否定しない態度でい続けることを心がけていましたね。実際、否定されるべきことって子供達に一個もなかったんですけど、日常会話でも一回も否定したことはなかったと思います。

――『世界』では「世界ってかっこいいんだ」というあきちゃんのセリフがありますが、あきちゃんからそういう言葉が出てきたのには驚きました。あのセリフに込めた想いをお伺いしたいです。
あれは実際にあきちゃんが言った言葉なんです。あきちゃんが吃音のことを書いた作文が学校で賞を取って、それが新聞に載ることになったんですけど、そのときあきちゃんはすごく戸惑っていて。「こんなダサい自分のことを書いているものを誰にも読まれたくない。」って連絡があったんです。
――そうだったんですね。
私はあきちゃんの作文は素晴らしいと思ったんですけど、「どういう作文だったら載ってよかったの?」と尋ねたら「世界のこととか、もっとかっこいいことを書きたかった。」と言われて。そのときに「あ、あきちゃんって世界のことをかっこいいと思っているんだ。」ってハッとしたんです。その言葉を聞いたとき、あきちゃんはすごいなと思ったと同時に、そういう世界じゃなきゃだめだなって思いました。あの言葉は、私にもすごく説得力があったし、世界にも伝わると思ったので、そのままあきちゃんのセリフとして使いました。

――監督自信お子さんがいらっしゃいますが、出産を経験されて子供達に対しての気持ちの変化はありましたか?
あの子達に対しても、この子に対しても、ずっと思う気持ちは変わらないですね。自由でいなさいって。自由でいられない世界になっちゃうと嫌だなと思っています。
――そのために自分がもっと働きかけようという思いになることはありますか?
そうですね。できるだけそうしたいです。
でも、子供が産まれて気づいたのは、意外と育児をさせてもらえることってほとんどなくて。みんな自分で勝手に成長しているんですよ。笑
知らないうちに寝返りを打ったり、歩き出してるんで、人間はちゃんと自分で成長して生きているんだと思いました。周りが育てるとか、周りがいたから大きくなれてるというよりも、自分が自分を育てていると思うんです。なので、私が子供にできることってほとんどないんだって思ったので、させてもらえる時にさせてもらいたいと思うぐらいです。
――確かに、満月もあきちゃんもすごく揺れ動いているけど、自分の中で戦っていて強いなと思いました。
そうですね。あの子たちは自分ですごい必死に生きていて、戦っていますね。

――『刻』は今どのくらい制作が進んでいますか?
『刻』は撮影を開始してから4年くらい経ちました。今は子供達が大学生になったりしているので、一旦撮影をお休みしています。大学って好きなことを自由にできる期間じゃないですか。一人暮らししたり、髪染めたり、好きなものを勉強するようになったり。
あの子たちが好きなことを好きにやれる最初の期間だと思うので、大学の間は撮らないと決めています。再来年くらいに撮影を再開できたらいいですね。
――監督がそれだけの時間をかけて映画を撮り続けられるエネルギーの源ってなんですか?
やっぱり興味ですね。あの子たちがどういう大人になるのかとか『刻』がどういう映画になるのか見たいという興味です。あとは、シンプルに生きていることはいつだって面白いからですかね。未来への興味と今の面白さです。常に面白いです。
――最後に『満月、世界』を見る方々にメッセージをお願いします。
子供達の未来が残る世界を残さないといけないし、そういう世界を残してくれ、あの子たちが光る世界であってくれと思います。
子供達に対しては、「あなたたちは光なので堂々と好きに生きなさい。」って伝えたいです。
02作品情報
『満月、世界』
9月21日(土)より渋谷ユーロスペースほか全国順次公開

(あらすじ)
『満月』
小説を書いたり、アイドル歌手の歌を聴いたりと、自分だけの世界を持っている、田舎の中学生、満月。高校への進学や、将来の進路を考えてながらも、当たり障りのない日常の中、彼女の感性は、生きること、死ぬことすら感じ取りながら、懸命に働いている。生き生きとしている彼女。だが、その繊細な十代の心の中には、未知の自分の可能性への不安がある。
『世界』
中学⽣の秋は吃⾳がある、授業中に発⾔を求められるが⾔葉が出ない。担任とも⾔葉のやり取りはない。本が好きな秋は、図書館で世界地図や社会問題の本をよく借りる。ススキが実る秋の川沿いの帰り道を洋楽を聴きながら帰る。家では⺟親がいつもピリピリしており、寝たきりで話せないおばあちゃんがいる。おばあちゃんの隣に座り込み借りてきた本を読む秋。ゆうみは⾳楽を⼈⽣にしてきた。好きで始めたはずなのに、焦りが生まれるようになっている。バイト先のバーではサラリーマンに好きな事を⼈⽣にしていてすごいと⾔われるが、何も言い返せない。夜の帰り道、⽬をつぶりながら⾃転⾞をこぐゆうみ。好きなこと、未来を⾒つめる2⼈の時間が、それぞれ流れていく
監督・脚本 塚田万理奈
1991年⻑野市出⾝。⽇本⼤学芸術学部映画学科監督コース卒業。卒業制作『還るばしょ』が、第36回ぴあフィルムフェスティバル⼊選、第8回⽥辺・弁慶映画祭⽂化通信社賞受賞、第12回うえだ城下町映画祭⾃主制作映画コンテスト審査委員賞受賞、第9回福井映画祭⼊選。初の⻑編映画となった『空(カラ)の味』が第10回⽥辺・弁慶映画祭で弁慶グランプリ・⼥優賞・市⺠賞・映検審査員賞と史上初の4冠に輝き、東京テアトル新宿、⻑野松⽵相⽣座ロキシー始め、全国公開を果たす。現在、16mmフィルムで10年かけて撮影する映画『刻』を制作中
公式サイト:https://movie.foggycinema.com/mitsukisekai/
Instagram:@toki.film
X:@tokifilm
『刻』プロジェクト
塚田監督「中学時代の友⼈たちとの再会を通し、10年間の彼らとの思い出を残しておきたい、みんなの⼈⽣を肯定したい、と思ったことから始まりました。「映画」をより「本物」にしたいと思い、実際に10年かけて、出演してくれる⼦どもたちの成⻑に寄り添って撮影することにしました」
クラウドファンディング:https://motion-gallery.net/projects/toki2024
photo:宇田川俊之
interview&text:Reika Hidaka