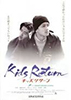MAGAZINE
Do it MagazineDo it Theaterが今気になるシアターカルチャーをクローズアップしてお届けする企画の[ Do it Close-up ]。今回は、『佐々木、イン、マイマイン』で映画ファンたちの心に火をつけた内山拓也監督の最新作『若き見知らぬ者たち』をクローズアップ。作品作りをサポートしてきた一人でもある株式会社ハッチ Producer 本間綾一郎さんと共に企画・宣伝の考え方や想いの伝え方、さらに監督が今の国内の映画シーンをどう捉えているのかお話を伺いました。
全国公開中
映画『 若き見知らぬ者たち 』
(Story)
風間彩人(磯村勇斗)は、亡くなった父の借金を返済し、 難病を患う母、麻美(霧島れいか)の介護をしながら、 昼は工事現場、夜は両親が開いたカラオケバーで働いている。
彩人の弟・壮平(福山翔大)も同居し、同じく、 借金返済と介護を担いながら、 父の背を追って始めた総合格闘技の選手として日々練習に明け暮れている。
息の詰まるような生活に蝕まれながらも、 彩人は恋人の日向(岸井ゆきの)との小さな幸せを掴みたいと考えている。 しかし、彩人の親友の大和(染谷将太)の結婚を祝う、 つつましくも幸せな宴会の夜、 彼らのささやかな日常は、思いもよらない暴力によって奪われてしまう。
01観る前も、観た後も考えられる伝え方
――今回、SNSやnoteなど映画を届けるという部分でもさまざまなこだわりを感じます。中でも1年前から制作過程を綴っているnoteのアイディアはどう生まれたのでしょう?
本間綾一郎(以下、本間):内山監督は常に新しいチャレンジや変化を意識している監督です。私自身もプロデューサーとしてその姿勢に共感しています。『若き見知らぬ者たち』においてはSNSの運用も映画宣伝だけのツールにせず、”新しい映画と観客の関係性づくり”ができないか?と模索してきました。企画から携わっているからこそ見れる景色を、後々伝えられるようにと準備してきたのが公式noteのはじまりです。
いちプロデューサー目線で見た内山監督の魅力は、映画を16対9のフレームのなかだけの物語に留めず、常に時代を意識した問いかけをもっている部分です。作家性と商業性の両立を目指して映画と向き合っているし、周り人の想いを汲むことにも責任を持っているから、役者もスタッフもついていきたくなるんだと思います。
 本間綾一郎 |株式会社ハッチ Producer。 1979年生まれ。大阪芸術大学芸術計画学科卒。 映写技師、映画宣伝、広告制作会社を経て、2013年にプロデュースカンパニー「HATCH Inc.」設立。 広告・番組・ブランディングなど領域を問わずクリエイティブに特化したプロデュースを行う。『若き見知らぬ者たち』共同プロデューサー。
本間綾一郎 |株式会社ハッチ Producer。 1979年生まれ。大阪芸術大学芸術計画学科卒。 映写技師、映画宣伝、広告制作会社を経て、2013年にプロデュースカンパニー「HATCH Inc.」設立。 広告・番組・ブランディングなど領域を問わずクリエイティブに特化したプロデュースを行う。『若き見知らぬ者たち』共同プロデューサー。
 内山拓也 | 1992年、新潟県出身。俳優の細川岳と共同で脚本を書いた『佐々木、イン、マイマイン』(20)で劇場長編映画デビュー。2020年度新藤兼人賞や第42回ヨコハマ映画祭新人監督賞に輝く。King Gnu「The hole」などのMV演出や広告映像を手がけ、「2021年ニッポンを変える100人」に選出される。『若き見知らぬ者たち』は待望の商業長編初監督作となる。
内山拓也 | 1992年、新潟県出身。俳優の細川岳と共同で脚本を書いた『佐々木、イン、マイマイン』(20)で劇場長編映画デビュー。2020年度新藤兼人賞や第42回ヨコハマ映画祭新人監督賞に輝く。King Gnu「The hole」などのMV演出や広告映像を手がけ、「2021年ニッポンを変える100人」に選出される。『若き見知らぬ者たち』は待望の商業長編初監督作となる。
――企画から関わっているからこそ、見える部分や届けられる内容も多そうですね。
本間:この作品を“どのように伝えるか”という議論は企画段階から重ねてきました。いろんなアイディアがあったなかで、結果的にnoteとInstagramが採用されることになりました。Instagramはビジュアルを扱うSNSなので、本編を観た後の印象と直結します。作品とInstagramを深く繋げることで新しい映画体験の連鎖みたいなものができないかと。それは作品の本質とずれてないことが大事だったし、観た人の共感を高めるものでないと意味がない。映画を作ることと同じくらいの労力を使って投稿を続けています。
内山拓也(以下、内山):以前から、noteはすごく魅力的な媒体だと個人的にも思っていたんです。使われ方が変わったらもっと魅力が広がって、さらに届いていくのではないかと。だから「映画×note」という形が、思いを馳せられる場所だったり、楽しみに待つ場所であったりすることにもできるのではないかと思いました。自分だけの寄り添える場所や、映画を観た後の追体験、いつ見ても咀嚼できるような場所にもなり得るのかもしれないと感じたので、プロデューサーチームと撮影前からnoteはやりましょうと話していました。

――発信する内容はどのように決めていったんですか?
本間:作品を届けるにあたって、内山監督と映画の追体験についてはよく話していたんです。答えを1つにして見せる作品ではなく、いろんな解釈や捉え方ができるように、“なぜそういう表現をしたのか”“何を大切にしてつくっているのか”という作り手の意思が伝わるような踏み込んだものを綴っていきたいと考えていました。
――映画を観たいと思わせるだけでなく、映画を観たあとも追体験を楽しめるようにと。
内山:『佐々木、イン、マイマイン』の時も、映画を観る前と観た後では感じ方が違うポスターにしたいという話をして、あのポスタービジュアルが出来上がりました。それがどこまで成し得たのかはわかりませんが、より作品に入り込むことができたとか、 ポスターを見た時にもう一度あの景色が思い返されるとか、いろんなお声をいただいたんです。
――その経験が、今回の映画を届けるという部分にも活かされているんですね。
内山:僕自身、これまで映画に人生を豊かにしてもらった経験がありました。映画は人の感情や営みを豊かにしてくれて、死ぬまで生きる力をくれるものだと感じていたんです。そういう恩恵をたくさんいただいてきたので、これからも届け方を意識したものづくりをしていきたいと思っています。そして、映画の内容だけでなく、どう届けるかということを観る前も、観た後も考えたいと思って生まれたのが、今回のnoteやInstagram、ノベライズやレコードです。
本間:映画製作では企画、制作、宣伝と各領域のプロデューサーが表現の責任も担っているんだというのが今回の発見でした。広告のお仕事はプロデュースとクリエイティブは役職で切り分けられる傾向があります。映画はより専門性の高いプロデューサーが両方を担いながら連携してくイメージです。広告と映画、両方の経験から見ると、内山さんがやろうとしていることは、クリエイティブディレクションに近いのかもしれません。映画館で観てもらうだけでなく、その映画体験の前後にも伝えたい想いがある。責任領域の課題はあると思いますが、このSNS時代において監督が届けるところまで役職として関与するということは重要なことなんじゃないかなと思います。

――映画はたくさんの方々と長い時間をかけて作られますが、どのようなコミュニケーションをとって想いを共有していたのでしょうか?
内山:友達と会ったり、先輩や後輩と話したりするのと同じです。間違っていることもあるかもしれませんが、僕は自分の誠意をまっすぐ伝えるということだけしかできない。だから、「これをやってみたいんです。そのためにはあなたの力が必要なんです」ということを、1人ひとりに話しにいくようにしています。「これでいいかな」みたいなことはあまりしたくないので。
本間:映画はいろんな人が自分ごととして携わって作られているものなので、そういう監督の想いの部分を受けて、個人個人が自由に解釈できるような環境をプロデューサー、監督、スタッフみんなで作っていったんだと思います。正解がないということもみんなで共有できていたし、「やりましょう」とポジティブに言ってくれる人が多くいたのは大きかった気がします。
内山:そうですね。正解はないと思っていますし、たぶん人生には100点なことなどないので、次にまた同じことを同じようにやるかというと、そうではない部分もあると思います。ただ、今回の現場では「共有する」ということを大事に、この作品における自分のステートメントはもちろん、音楽のプレイリストなども共有していました。

02 自分たちのスタイルを確立しながら、どう取り入れていくか
――『若き見知らぬ者たち』は、日本、フランス、韓国、香港製作の映画です。今後日本でこういう体制で作られる作品は増えていくと思いますか?
内山:以前よりも、端的な海外というワードは確実に出るようになっています。ただ物価が上がっている感覚とも似ていて、それは映画に限らず他の業界でも世界に対する意識はあると思っています。でもそういうなかで、日本映画はどうやって太刀打ちしていくのかを考えたときに、諸外国がおこなっている合作とはまだ少し距離があるように感じています。
――それはなぜでしょう?
内山:例えば、合作をすることで国内、海外双方の内容のメリットを見出すのがポジティブかつビジネス的であると思うのですが、海外の方と一緒につくることで、何を獲得していくかという部分はまだまだ追いつけていないのが現状なのかもしれません。でも、海外のお客さんに観てもらう機会が増えることで、どう届いてどう感じるのかという視点は、10年前より確実にあると感じています。
だからこそ、経済と一緒で、映画業界も諸外国を参考にしながら自分たちのものを確立していかないといけない時代になってきている。でも、まだ本当に途中だと思うので、どこまで成長できるかは、今映画に携わっている人たちの力にかかっているというフェーズだという気はしています。
――さまざまな国のスタッフの方と一緒につくるのは、いろんな面で面白さがありそうです。
内山:今回ご一緒した方々は、みなさんものづくりに真剣で、かつ人生を楽しむことにも真剣で、そこがいいなと感じました。1つひとつの経験から語られる想いがものづくりのチューニングになっているから、「なんでそうしたいんだ」とか「どうしたらこうなるんだろう」とか、その本質を見ようとする行為がずっとあるんです。ゴールはわからないけど、「こっちの方がもっと良いのではないか」とか「これはなんでだと思う?」みたいな会話をしている時間は僕にとってとても刺激的でした。

03映画の未来に繋がる糸口とは?
――コロナ禍を経て、映画を取り巻く環境もさまざまな形で変化していっているさなかですが、お二人は現在の国内の映画シーンをどう捉えているのでしょうか?産業でいうと、各地の歴史あるミニシアターの閉館も続いています。
内山:そうですね。ミニシアターが閉館の危機に瀕していることを、作り手も同時に発信したり感じたりすることが大切ですし、誰かが感じて受け取ったものをリレーして、次の世代へ繋げていくことが必要かなと思っています。
映画づくりをする楽しさは、自国を見つめて掘っていくことで、異文化の交流になっていくこと。そして、言語や文化を超えて共有できる、もしくは発見してもらえるものが映画の面白さなのではないかと思っています。映画は、さまざまな国と引き寄せ合いながら、影響を及ぼし合いながら、その時代とともにあるものなので、日本の産業だけで考えてはいけないと思うんです。つくる人も受け取って発信してくれる人もどんどん変わっていく。だからこそ、業界は長期的に見ていく必要があると思っています。
本間:映画産業の変化は強く感じています。かつては、多くの予算をかけた大衆映画はメジャーと呼ばれ、作家性の高いものはミニシアターと分けられていた時代がありましたが、それは僕が憧れていた90年代、2000年代の話で、現代ではそういったわかりやすい線が見えにくくなってきている。出資する側も商業性の文脈なのか、アート性の文脈なのか、境目の判断が難しくなっていて、作品を作る意義や必然性が明覚であることが重要になってきていると思います。
――移り変わりの激しい時代に、何を意識することが重要だと思いますか?
内山:変化は良くも悪くも数年ごとに訪れるので、今日本映画が盛り上がっていると感じられるならば、だからこそ今世界にどう見られているんだろうかとか、今後どういったものを届けていかないといけないとか、全体で共有していかないと、一過性で終わってしまいますし、「そんな年もあったね」みたいなことにしかならない。もちろん、つくられた映画やものづくりの形は残ると思うんですけど、産業としては全体で底上げしていく必要があると思います。
本間:時代の匂いとして感じるのは、「作り手の想い」なのかなと。内山監督が描こうとしている物語は新しさもあるしどこか90年代にあったような懐かしい感じもします。内山監督のような意思のある作家が時代に求められていると感じているからこそ、一緒にその先を見ていきたいし、できることを少しずつ一緒にやっていきたいと思っています。
内山:いいものをつくるということは、新しいものをつくることだと思います。物語や内容のクリエイティブはもちろん、映画のつくられ方や見せ方、どういう人とどういう風にやるかというところも含めて、みんなで同じ旗を立てて、共有しながら制作をしたいですね。
そして、普段自分が仕事をしながら、本間さんをはじめ、映像や広告の仕事でご一緒している方々の視野の広さや面白さは実感しています。それらを映画と融合していくことによって、映画の未来に繋がる糸口の1つになるのではないかと考えていました。これまで築いてきた歴史を重んじながらも、新しいことを取り入れてチャレンジしていきたいです。

04作品情報
映画『若き見知らぬ者たち』
2024年10月11日公開

(Story)
風間彩人(磯村勇斗)は、亡くなった父の借金を返済し、 難病を患う母、麻美(霧島れいか)の介護をしながら、 昼は工事現場、夜は両親が開いたカラオケバーで働いている。
彩人の弟・壮平(福山翔大)も同居し、同じく、 借金返済と介護を担いながら、 父の背を追って始めた総合格闘技の選手として日々練習に明け暮れている。 息の詰まるような生活に蝕まれながらも、 彩人は恋人の日向(岸井ゆきの)との小さな幸せを掴みたいと考えている。
しかし、彩人の親友の大和(染谷将太)の結婚を祝う、 つつましくも幸せな宴会の夜、 彼らのささやかな日常は、思いもよらない暴力によって奪われてしまう。
原案・脚本・監督:内山拓也
出演:磯村勇斗、岸井ゆきの、福山翔大、染谷将太、伊島空、長井短、東龍之介、松田航輝、尾上寛之、カトウシンスケ、ファビオ・ハラダ、大鷹明良、滝藤賢一、豊原功補、霧島れいか
企画・制作:カラーバード
配給・宣伝:クロックワークス
企画協力:ハッチ
© 2024 The Young Strangers Film Partners
Website:https://youngstrangers.jp
note:https://note.com/youngstrangers
Instagram:@youngstrangers_movie
X:@youngstrangers
photo:Cho Ongo(@cho_ongo)
interview&text:Sayaka Yabe