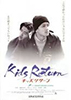MAGAZINE
Do it MagazineDo it Theaterが注目のシアターカルチャーをクローズアップしてお届けする企画[Do it Close-up]。今回は、人生で直面するさまざまな“呪い”をコミカルかつ辛辣にあぶり出す映画『恋脳Experiment』の主人公・仕草を演じる祷キララさんにインタビューしました。学生時代、祷さん自身も「進学するのが当たり前」という考えに縛られていたといいます。苦悩の日々からどう抜け出し、どのようなエネルギーで前進したのか。祷さんの体験を元に、本作を通じて学び、成長できたことをお伺いしました。また、映画の世界に入るきっかけとなった原点となるシアター体験についてもお話しいただいています。
2025年2月14日(金) 新宿シネマカリテほか全国順次公開
幼い頃からおままごとや絵本に囲まれ、素敵な異性との出会いに憧れてきた主人公・仕草(しぐさ)。中学生になり「恋をすると可愛くなれる」と聞き、早速同じ塾の男子に告白して付き合うことに。期待に胸をふくらませるが、その先には思いがけない展開が待ち受けていた。「可愛いね」と耳元でささやく塾講師、芸術家気取りの高プライド彼氏やセクハラ&パワハラ上司、そしてついに出会えた優しく理想的な男性――彼らとの出会いを通し、仕草は自分にかけられていた“呪い“に気づき、自身と向き合っていく。
01「絶対にこのままで終わらせない!」—— 祷キララを動かすエネルギー
──最初に脚本を読まれたとき、ご自身の役・仕草のことをどう感じましたか?
私は「わかるな」と思うところがたくさんありました。
仕草は失恋をするとそのエネルギーを一気に仕事にぶつけるみたいなところがあるんですけど、私自身も負けず嫌いなところがあって。失恋したり、やりたかった仕事ができなかったりすると、「絶対にこのままで終わらせてたまるか!」という気持ちになるんです(笑)。
そうすると、いつも以上にパワーが湧いてきて。そういうエネルギーの発露の仕方や、「このままじゃ終われない」と奔走する感じは、自分にも覚えがあって共感しました。
 祷キララ(山田仕草 役) | 2000年3月30日生まれ。大阪府出身。 2015年公開の映画『Dressing UP』(安川有果監督)で映画初主演を務め、「第8回シネアスト·オーガニゼーション大阪」CO2新人賞、「第14回 TAMA NEW WAVE」ベスト女優賞などを受賞。『ハッピーアワー』(15/濱口竜介監督)、『サマーフィルムにのって』(21/松本壮史監督)、『忌怪島/きかいじま』(23/清水崇監督)、『HAPPYEND』(24/空音央監督)など話題作に出演。テレビドラマは「シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。」(20/ytv)、「瑠璃も波瑠も照らせば光る」(22/CX)、「孤独のグルメseason10」(22/TX)や、AppleTV +配信中のドラマ『PACHINKO2』にも出演。
祷キララ(山田仕草 役) | 2000年3月30日生まれ。大阪府出身。 2015年公開の映画『Dressing UP』(安川有果監督)で映画初主演を務め、「第8回シネアスト·オーガニゼーション大阪」CO2新人賞、「第14回 TAMA NEW WAVE」ベスト女優賞などを受賞。『ハッピーアワー』(15/濱口竜介監督)、『サマーフィルムにのって』(21/松本壮史監督)、『忌怪島/きかいじま』(23/清水崇監督)、『HAPPYEND』(24/空音央監督)など話題作に出演。テレビドラマは「シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。」(20/ytv)、「瑠璃も波瑠も照らせば光る」(22/CX)、「孤独のグルメseason10」(22/TX)や、AppleTV +配信中のドラマ『PACHINKO2』にも出演。
──仕草は、作品作りを通じて悩みや自身の思いの丈をアウトプットしていたように思います。祷さんはいかがですか?
私も悩み事があると演技や役作りにもっと没頭しようと思ったり、「眠いけど街に出て映画を観てみよう」「気になっていた人に連絡してみよう」といった行動に繋がることが多いです。仕事の準備に熱を入れたり、自分のやりたいことに向けて地盤を固めようとする感じで、人に会ったり、外に出たりすることが増えるかなと思います。
──なるほど。自分の中で悩むよりも、外に出ていろんなものに触れながら考えを深めていくんですね。
そうなんです。私はめちゃくちゃ外に出るタイプです。思い悩むより行動する方が多いかもしれません。
──小さい頃からすぐ行動に移せる性格でしたか?
どうだったかな…?特に10代の終わり頃の経験がきっかけで、苦しい状況になっても「絶対にこのままでは終わらせない!」というマインドが染みついたように思います。
高校3年生のとき、「この仕事をやっていこう、上京しよう」と決断したものの、ちょうど進路を決める時期で、先生や友達と将来の話をするたびに不安になっていました。
進学校に通っていたので「大学進学が当たり前」という雰囲気が強く、息苦しさを感じていて。自分も無意識のうちにその考えが当たり前になっていたので、決断するまでの過程は本当にしんどかったですね。

02当たり前から抜け出すきっかけ
──そこから祷さんは大学進学と仕事の両立の道を選ばれましたが、その選択をすることになった一番のきっかけは何だったのでしょうか?
やっぱり、「この仕事がやりたい!」と強く思えたことだったと思います。
進路を決める時期は本当に苦しくて、ずっと何かを探しているような感覚がありました。そんな中、東京でオーディションを受ける機会があって。
オーディションで芝居をしているとき、「あ、私はこれが楽しいんだ」と心から実感したんです。たぶん、あれだけ悩んでいたからこそ、「これだ!」と思えた瞬間に迷わず飛びつけたんだと思います。
──別の選択を見つけられたんですね。
そうですね。その思いがあったからこそ、「大学進学が当たり前」という考えから一瞬でも離れられて、客観的に自分を見つめ直せました。「大学には行くけど、この仕事もやる」、その選択肢なら自分に合うんじゃないか、と考えることができたんです。
もちろん、色々な選択肢に気づいたからといってすぐにその考えから抜け出せたわけではありません。でも、「自分のやりたいことを続けるために大学に行こう」と思えたことで、同じ進学という選択でも気持ちがすごく楽になりました。

03言葉から解き放たれた身体表現
──作品の中では、平井亜門さん演じる同級生で恋人の佐伯翔太との関係が、そういう囚われからの開放のきっかけになっていましたよね。特に最後のダンスのシーンが印象的でしたが、どのように作り上げていったのでしょうか?
あのシーンは、まずめちゃくちゃ練習しました笑。亜門君と一緒にコンテンポラリーダンサーの方を招いて、ワークショップのような形で、一緒に体を動かすのに慣れることから始めました。
ただ、私の役はダンサーではないので、単に「上手く踊る」ことが求められているわけではなくて。だから、表現の仕方のアイデアをたくさん教えてもらいましたね。
「こういう気持ちのときは、こんな動きができるよ」とか、「こうやって動いてみたらどう?」とか。そういうアプローチで、自分の体と心を一致させていく練習をしました。ダンスというより、「心を主体にして体を動かす」感覚を研ぎ澄ましていくイメージです。
──色々な表現方法を学んで、組み合わせていくような?
そうですね、振り付けが厳密に決まっていたわけではなく、アイデアを2人で取り入れながら作っていきました。芝居と同じように、受けて返すコミュニケーションの形が、言葉から解き放たれて身体で表現されるような感覚でした。
──監督からは何かアドバイスはありましたか?
監督からは「子供の頃、今だけのことに夢中になって遊び疲れていたような感覚でやってほしい」とだけ言われて。だから、たくさん学んで準備をした上で、あとは亜門君と本当に遊ぶように、ヘトヘトになるまで試行錯誤していきました。

──そのシーンの撮影中、ご自身の気持ちの変化はありましたか?
ありましたね。あのシーンって、最初からお互い心を開いている状態ではなく、仕草は閉じた状態から始まるので、本当に丁寧に演じると時間がかかるシーンでした。
でも、撮影が進むにつれて、最初は恥ずかしいなとか「どう動けばいいんだろう?」と考えていたのが、体を動かしていくうちに、どんどん考えなくなってきて。気づいたら、「今、この瞬間を楽しんでいる」という感覚になっていました。
──映画の中でのダンスシーンにも、その変化が伝わってきて、とても心に響きました。参考にした映画や芸術などはありましたか?
そういえば、監督からいくつか映画を観るように勧められました。『レザーフェイス 悪魔のいけにえ』なんかは特に印象的で、チェーンソーを振り回す殺人鬼の姿がイメージに近いと言われましたね(笑)。他にも韓国映画で、殺人を犯した息子の母親が出てくる作品を観たのですが、その映画の中でも、ある出来事を経てキャラクターがすべてから解き放たれるようなシーンがあって、そういう「エクスタシー」的なものがラストのダンスシーンの参考になっていました。

04映画を通じて学んだ視点の変化
──この作品を通して、ご自身の成長を感じたことはありましたか?
ありましたね。脚本を読んで準備している時に、「あの時はこういうことに縛られていたな」と気づく瞬間があって。
例えば、役作りの時に、仕草は「恋愛をしなければ幸せになれない」という呪縛から解き放たれようとしているキャラクターということに私自身が縛られていて。でも、人間って恋愛をしたい時もあれば、したくないけど「した方がいいのかな?」って思う時もあるし、純粋にしないでいいやって思うときもある。そういういろんな時期があって、人間って一面的なものじゃないんだなって。
そういうことを監督と話していると、自分もいろんなことに囚われているなって気づくことが多かったです。役作りをする中で、「こだわってしまう部分が自分にもあるな」と思うことがあって。でも、それを理解しておくと、また違った視点が持てるんだなと感じました。
──気づかないうちに自分自身を縛ってしまうことってありますよね。
そうですね。自分の場合、お金の使い方もそうで。「計画的に使わないといけない」と思っていたけど、本当は自分が稼いだお金なら自由に使っていいはずなんですよね。頑張ったからちょっと無理して買って、その分仕事を頑張るのもアリだし、貯蓄するのもアリ。でも、どちらかに縛られてしまうことがある。そういう小さなことでも、「あ、今自分はこういう考え方に囚われていたんだ」って気づくことが大事だなって、この映画を通して学びました。
──祷さんが大学進学と上京を決めた時の経験と重なる部分がありますね。
そうですね、今話していて自分でもそう思いました(笑)。

05「映画館での出会いが人生を変えた」──祷キララさんの原点となったシアター体験
──祷さんにとって、記憶に残っているシアター体験って何かありますか?
ちょっと昔の話ですが、この仕事を始めたきっかけが映画館での出来事なんです。小学4年生の頃にスクリーンデビューしたんですが、その2年前、7歳くらいの時に両親に連れられて大阪の梅田にある映画館へ、両親の友人だった監督の映画を観に行ったんです。
その時に観たのが『青空ポンチ』って映画でした。あまり内容は覚えていないのですが、夏が舞台で、音楽がすごく印象的でした。
──ストーリーは覚えていなくても記憶に残っている映画ってありますよね。
そうそう。内容とか技術的なことは7歳だったので全然わからなかったんですけど、映画館での体験そのものがすごくワクワクしたんですよね。大きなスクリーン、迫力ある音、会場の雰囲気……「うわ、映画ってすごいな!」って思いました。
──映画館ならではの体験ですね。
その後の打ち上げで監督がいて、「この映画を作った人なんだ!」って感動したんです。何も考えずに「いいなぁ、映画!キララも出たい!」って言ったらしくて(笑)。それを監督が覚えてくれていて、2年後に新作を作る時に「じゃあ、キララが出る役を書くよ」って言って、本当に役を作ってくれたんです。
──まさに人生を変えたきっかけが映画館だったんですね。
そうなんです。映画館で映画を観たあの瞬間が、今に繋がっています。作品の内容どうこうじゃなくて、「映画館の空気感」みたいなものに圧倒されたのを覚えています。
親は友人の映画だから軽い気持ちでだったと思うんですけど、私にとってはものすごく大きな体験になりました。あの時、映画館に行かなかったら、今こうして映画に関わっていなかったかもしれません。
06作品情報
2025年2月14日(金) 新宿シネマカリテほか全国順次公開
 (Story)
(Story)
幼い頃からおままごとやお姫様ごっこをして遊ぶのが好きだった山田仕草(やまだしぐさ)。中学生になり、女子校に通う仕草(大月美里果)は、塾からの帰り道、同じ塾に通う晴人と女子がケンカをしているのを見かける。ひとりになった晴人を、仕草は追いかけて声をかける。「もしよかったら私と付き合ってください!」。晴人は、名前も知らない仕草からの突然の告白に驚きながらも二つ返事でOKする。しかし、その後、仕草には思いがけない展開が待ち受けていた。数年後、美大生となった仕草(祷キララ)は、就職活動中。同級生の恋人・佐伯翔太(平井亜門)は、コンテンポラリーダンスに情熱を注いでいる。佐伯は自分が取り組んでいる卒業制作について熱く語り、仕草の話に耳を傾けないばかりか就活をする同級生たちをこき下ろす。後日、自分が卒業制作の準備がうまく行かない原因は恋愛をしているせいだと思い、仕草に一方的に別れを告げる。大学を卒業後、デザイン事務所に就職した仕草は、憧れのデザイナー・西川(小林リュージュ)の下で働き始める。西川はセクハラ、パワハラが常習化していた。休日、仕草は西川の自宅で開催されるホームパーティに呼ばれるが、そこでもこきつかわれる。そんな中、ホームパーティに参加していた西川の元同僚・金子エイジ(中島歩)は、仕草の姿を見かねて手伝ってくれる。仕草はついに“理想的な男性”に出会えたかに見えたのだが…。
監督:岡田詩歌
出演:祷 キララ、平井亜門、中島 歩
河井青葉 、大月美里果 、佐藤和太 、二見悠、中山雄斗、 門田宗大、関谷翼、小林リュージュ、小野まりえ、川郷司駿平、佐藤京、中島多羅
脚本:岡田詩歌、岡田和音 プロデューサー:天野真弓
撮影:熊倉良徳 照明:大和久 健 録音:豊田真一 美術:井上心平、園部陽一郎 アニメーション:岡田詩歌、農場 音楽:糸井塔 編集:高橋幸一 整音:横山大資 助監督:川田真理 ラインプロデューサー:仙田麻子 制作担当:原 夢之助
<第29回PFFスカラシップ作品>
2023年/カラー/110分/DCP 英題:Kisspeptin Chronicles ©2023 ぴあ、ホリプロ、電通、博報堂DYメディアパートナーズ、一般社団法人PFF
配給・宣伝:ストロール
公式HP:rennou-experiment.com
公式X:@rennou_ex
公式Instagram:@rennou_experiment
photo:Cho Ongo(@cho_ongo)
interview&text:reika hidaka
hair&make-up::根本佳枝
stylist:和田ミリ
brand:トップ、スカート¥110,000/YOHEI OHNO、その他スタイリスト私物